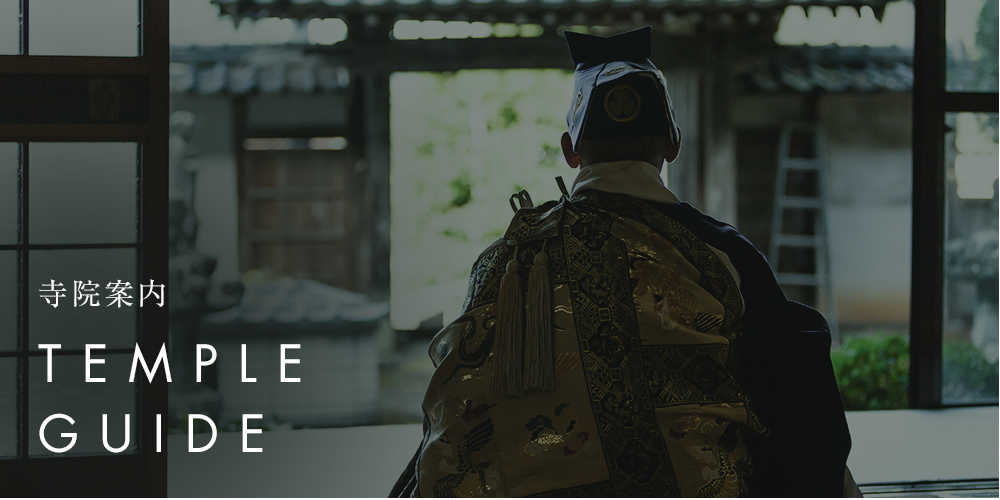法要とは?

一般に、「法事」と言われていますが、厳密に言いますと、住職にお経をあげてもらうことを「法要」といい、法要と後席の食事も含めた行事を「法事」と呼びます。
そもそも法要は故人を偲び、冥福を祈るために営むものです。
冥福とは、冥途の幸福のことで、故人があの世でよい報いを受けてもらうために、この世に残された者が供養をします。
また法要は、故人が設けてくれた人と人とのご縁、「この人がいたから自分がいる」というつながりを再確認し、故人への感謝の思いを新たに、自分自身を見つめ直す場でもあります。
法要を営む日
忌日法要
| 初七日 | しょなのか | 命日も含めて7日目 |
| 二七日 | ふたなのか | 命日も含めて14日目 |
| 三七日 | みなのか | 命日も含めて21日目 |
| 四七日 | よなのか | 命日も含めて28日目 |
| 五七日(=三十五日) | いつなのか(さんじゅうごにち) | 命日も含めて35日目 |
| 六七日 | むなのか | 命日も含めて42日目 |
| 七七日(=四十九日) | なななのか(しじゅうくにち) | 命日も含めて49日目 |
| 百ヶ日 | ひゃっかにち | 命日も含めて100日目 |
年忌法要
| 一周忌 | 命日から満1年目 |
| 三回忌 | 命日から満2年目 |
| 七回忌 | 命日から満6年目 |
| 十三回忌 | 命日から満12年目 |
| 十七回忌 | 命日から満16年目 |
| 二十三回忌 | 命日から満22年目 |
| 二十七回忌 | 命日から満26年目 |
| 三十三回忌 | 命日から満32年目 |
| 三十七回忌 | 命日から満36年目 |
| 四十三回忌 | 命日から満42年目 |
| 四十七回忌 | 命日から満46年目 |
| 五十回忌 | 命日から満49年目 |
| 百回忌 | 命日から満99年目 |
初七日から百カ日
初七日
命日も含めて七日目に行うのが初七日。
故人が三途の川のほとりに到着する日とされています。故人が激流か急流か緩流かのいずれを渡るかがお裁きで決まる大切な日で、緩流を渡れるように法要をします。
初七日は骨上げから二~三日後となります。遠来の親戚に葬儀後、再び、集まっていただくのは大変なので、葬儀の日に遺骨迎えの法要と合わせて行うことが多くなっています。
四十九日までの遺族の心得
葬儀のあと、遺骨、遺影、白木の位牌を安置し、花や灯明、香炉を置くための中陰壇(後飾り壇)を設けます。
中陰の四十九日間、家族は中陰壇の前に座り、故人が極楽浄土に行けるように供養します。
一般には四十九日までが忌中(きちゅう)で、この期間は結婚式などのお祝いごとへの出席や、神社への参拝は控えるようにします。
位牌の準備
白木の位牌は、葬儀の野辺送りに用いる仮の位牌です。四十九日法要までは、遺骨、遺影と一緒に中陰壇にまつりますが、四十九日までに漆塗りの本位牌に作り替えなくてはなりません。戒名の文字入れに2週間位かかるので、早めに仏壇店に依頼しておくとよいでしょう。
四十九日法要を終えた後、本位牌は仏壇に安置しますので、仏壇のない家は四十九日までに手配が必要となります。
白木の位牌は、四十九日法要の時に菩提寺に納め、新しく作った本位牌に住職から魂入れをしていただきます。お寺で四十九日法要を営むときは、本位牌を持参して魂入れをお願いし、帰宅後、仏壇に安置します。
四十九日当日
四十九日は、初七日から七日ごとに受けたお裁きにより来世の行き先が決まるもっとも重要な日で、「満中陰(まんちゅういん)」と呼ばれます。
故人の成仏を願い極楽浄土に行けるように、家族や親族のほか、故人と縁の深かった方々を招いて法要を営みます。
そして、この日をもって、「忌明け(きあけ)」となるので、法要後、忌明けの会食を開きます。
法要は忌日(きび)の当日に行うのが理想ですが、実際には参列者の都合もあり、最近は週末に行うことが多いです。法要の日をずらす場合は、遅れてはいけないとされています。
四十九日は、それまで喪に服していた遺族が日常生活にもどる日でもあります。
百カ日
百カ日は、亡くなった命日から数えて100日目の法要です。
「卒哭忌(そつこくき)」ともいわれ、泣くことをやめ悲しみに区切りをつける日で、家族や親族などの身内で法要を営むことが多いです。
百カ日以降の法要
一周忌
故人が亡くなってから一年後の命日が一周忌で、家族や親族のほか、故人と縁の深かった友人や知人を招いて法要を営みます。
法要は命日の当日に行うのが理想ですが、実際には参列者の都合もあり、最近は週末に行うことが多いです。必ず命日より早めの日に行うのが慣わしです。
一周忌までが喪中(もちゅう)で、この日をもって喪(も)が明けることになります。喪中に迎えた正月は、年賀状、年始挨拶、正月飾り、初詣などの正月行事は控えます。
年忌法要
一周忌と三回忌は四十九日法要に次いで大切な法要です。親族を招いて、規模の大きな法要を営みます。
まず、住職と相談をして、法要を営む日を決めます。法要の日に卒塔婆を立てる場合は、事前に住職に依頼しておきます。
次に、法要場所を自宅か、菩提寺、あるいは斎場で行うかを決めます。法事を菩提寺以外で営む場合は、「御布施」とは別に「御車代」を包むのが一般的です。また住職が会食を辞退された場合は、「御膳料」を包む場合があります。
日取り、場所が決まったら、招待客を決め、1ヵ月前には案内状を送り、返事をもらいます。参列者の人数が確定してから、会食、引き出物を用意します。引き出物は一所帯に一個でよいとされています。法事の際の服装は、施主側は略礼服を着用し、数珠を忘れずに持参します。
一周忌と三回忌は必ず、ひとりの法要を営みます。七回忌以降は同じ年に法要が重なった場合、まとめて行ってもよいとされ、法要を行う日は、あとに亡くなった故人の命日にあわせます。案内状には誰と誰の法要かを必ず明記します。これを「併修」あるいは「合斎」といいます。
お盆・お彼岸について
お盆の仏教的意味
仏教行事としてのお盆は、仏説盂蘭盆経(ぶっせつうらぼんきょう)に基づくものです。
お釈迦さまの弟子であった目連尊者が、7月15日に多くの僧侶たちに供物を施し供養することによって、餓鬼道に落ちて苦しんでいる母親を救い出すことができたという言い伝えによります。
以来7月15日は、故人や先祖に報恩感謝をささげ供養をつむ重要な日になったのです。お盆に多くのお寺では、餓鬼道や地獄に落ちて苦しんでいる霊を救うための施餓鬼会(せがきえ)と呼ばれる法要を営みます。
お盆(送り火・迎え火)
お盆は、正式には盂蘭盆会(うらぼんえ)といいます。故人や先祖の霊が、一年に一度家に帰って来るといわれており、その霊を迎え供養する期間がお盆です。
お盆の前日には、故人や先祖の霊を迎える準備をします。精霊棚(しょうりょうだな)(盆棚)か仏壇に、精進料理を供えた霊供膳(仏膳)や、季節の物を供えてお盆のしつらえをします。13日の夕方に、家の前で焙烙(ほうろく)という素焼きの皿の上でおがら(麻がらのこと)を焚いて、「迎え火」として故人や先祖の霊を迎えます。
墓参りをしたあと、墓地で盆提灯に明かりを灯し、霊を自宅まで導いて帰ってくるという風習を行う地域もあります。
この時期に、菩提寺の住職が檀家を回ってお経をあげる、棚経(たなぎょう)を行います。
16日には再び火を焚いて「送り火」として送り出します。京都の有名な大文字焼きも送り火のひとつです。
実際に火を焚くのがむずかしい場合は、盆提灯を飾って迎え火、送り火とします。盆提灯はその家に霊が滞在しているしるしとされています。
新盆・盆提灯
新盆は四十九日の忌明け後に迎える初めてのお盆のことで、「にいぼん・しんぼん・はつぼん」などと呼びます。家族や親戚が集まり、手厚く供養します。
四十九日を迎える前にお盆が来たときは、翌年が新盆になります。故人の霊がはじめて帰ってくるお盆なので、霊が迷わないように、お盆の間、軒先や仏間に新盆用の白提灯をつるします。
仏壇の両脇や精霊棚の両脇に絵柄の入った盆提灯を一対、二対と飾ります。飾るスペースがないときは、片側に一つだけ飾る場合もあります。
新盆用の白提灯は、玄関や縁側の軒先や、仏壇の前に吊るします。白提灯はローソクの火を灯せるようになっていますが、危ないので火を入れないで、ただお飾りするだけで迎え火とする場合も多いです。
新盆用の白提灯は送り火で燃やしたり、菩提寺で供養処分してもらいます。それができないときは、火袋に少しだけ火を入れて燃やして、形だけお焚き上げにしてから、火を消して新聞紙などにくるんで処分してもよいです。
絵柄の入った盆提灯は毎年飾るものなので、火袋のほこりを払い落とし、部品をよく拭いてから箱に保管しておくと良いでしょう。
精霊棚
盆棚ともいいます。
多くの地方では12日か13日の朝に、故人や先祖の霊を迎えるための精霊棚(しょうりょうだな)をつくります。仏壇の前に小机を置き、真菰(まこも)のゴザを敷いて精霊棚をつくります。その上に、位牌を中心に安置し、香炉、花立、燭台を置き、お花、ナスやキュウリ、季節の野菜や果物、精進料理を供えた霊供膳(仏膳)などを供えます。
故人や先祖の霊の乗り物として、キュウリの馬とナスの牛を供えるのも昔からの慣わしです。霊が馬に乗って一刻も早くこの世に帰り、牛に乗ってゆっくりとあの世に戻っていくようにという願いが込められています。
精霊棚をつくるスペースがないときは、仏壇のなかに供えてもかまいません。
供養とは?
供養は供える物より、その行動をする人の心が重要です。また品物だけでなく、為になる話をしたり、仏教的教えに基づいた行いをすることも供養です。
お経をあげるのは、為になる具体的行動です。行供養とか法供養、敬供養などといいます。参会した人への食事の提供や、お寺に仏具などを奉納するのは、財供養または利供養といいます。
また、供養の語源には”彩る”と言う意味もあり、美しいものを供えることも供養です。花をはじめとして、本堂の中にあるきらびやかな瓔珞ようらくや幢幡どうばんなどの飾り物も、供養品のひとつです。

主な供養の種類
先祖供養(祭祀)
インド仏教では、仏・法・僧の「三宝」を供養することが本来の供養でありました。
中国仏教では、直接、先祖や亡き父母を(霊廟で)祭祀する儒教の「先祖祭祀」の考え方が取り入れられ日本に伝わりました。
彼岸供養
お彼岸とは中日を挟んで前後三日間の、合わせて一週間の行事です。お中日とは太陽が真西に沈む春分・秋分の日です。
昔から西には西方浄土といって仏の世界があり極楽とされています。
極楽に往って生まれた(往生)先祖を偲び、今日ある自分を育んでくれた先祖に感謝し、自分も死なば極楽浄土に行きたいと決意を新たにする実践週間です。
永代供養
仏の供養をするべき施主が遠くに住んでいたり、海外へ移住したり、子供がいなくて法要を勧めてくれるひとが居ないなど、やむをえない事情で、法要ができないときに、代わって菩提寺が永久に祖先に対する法要をしてくれるのが永代供養です。永代供養とは文字通り、永久に子々孫々までご先祖さまを供養することです。
ただ現在では一般の墓苑業者や葬儀社の方々が少し意味の異なる解釈をしているようです。彼等には内規があって、五十回忌くらいまでを指して、いわゆる永い間というような意味でとらえているようです。ここではその正しい解釈ともう少し広義で考えてみることにします。
正しくは永代で供養するのですからお寺の方から考えますと住職の代が変わっても変わらず供養すると言うことです。
当地では祠堂施餓鬼という内容でお施餓鬼に毎年供養をするのが一般的ですが、永代供養とはその家が絶えてしまう時にご先祖をお寺において永久に供養すると言う考え方が一般的です。
絶えてしまうというと穏やかでは無いですが、子供さんがいらっしゃらないとか娘さんだけですでに他家へ嫁いでおられるとかでご先祖のお守りができなくなってしまう例はけっこうあります。嫁してしまうと娘さんも嫁ぎ先の仏様がありますから実家の方まで面倒をみられないという状態です。
ただこれは一例として特に思いの強いお世話になった方の供養をご依頼になりこともあります。この場合は血縁でなくてもかまわないと思います。その他には人間だけでなくて特に可愛がっていたペットやお人形などもこの範疇に入ってきます。
まとめてみますと、本人が何らかの理由で祭祀できない環境にあるかまたはそれになる可能性がある場合などに本人様に代わってお寺がその役を遂行することでしょう。
これには今まで述べてきた理由に加えて お墓や実家と遠距離に勤務なさっているとかお体が不自由で直接お参りに行けなくなってしまった場合も含まれます。
当山では永代供養の定義付けを文字通り永久にと考えております。ただこれはやはり特別なことであって、本来は縁につながる方々が故人を偲んでお参りすることが肝要でしょう。
水子供養
水子供養とは、生まれることのなかった我が子を慈しみ生むことのできなかった母の心を癒すご供養です。
先祖供養
先祖供養と言うと、なんとなく時代錯誤のようなイメージを持たれる方も多いと思います。しかし、今の私たちが在るのは先祖があって初めて成り立つのは皆様にもご理解いただけるところでしょう。だからこそ、人はお墓や仏壇の前で手を合わせ、先祖を敬い、懐かしんで、今は亡き人々への祈りを捧げるのです。
信仰する宗教や、人それぞれの考え方によって、先祖の霊と言うものに対する立場は様々でしょうけれども、不思議とお墓や仏壇に参った時に心の安息を感じるのは多くの人に共通するのではないでしょうか。
先祖供養と言っても何も難しく考えることはありません。辛い時、悲しい時、そして何か心に不安を感じた時にはお墓に参ったり、仏壇に手を合わす。そして父母や祖父母、さらに昔の先祖の霊に祈れば、親が子供を慈しむように先祖の霊は必ず救いの手を差し伸べてくれることでしょう。墓参や、仏壇に手を合わせることで先祖の霊には供養となり、私たちには心の安息が得られるのです。
父母や祖父母が先祖となって私たちを見守ってくれるように、やがて私たちも先祖となり子や孫を見守っていきます。そのように生者と死者の間で人の営みは永遠に繰り返されて行くものです。
先祖供養、それは、故人の霊のためでもあると同時に生者のためでもあるのです。先祖の霊に手を合わせることで、心の平安が得られるのであれば、先祖供養は人々の心の支えとなるのではないでしょうか?